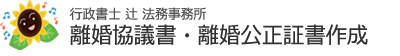面会交流の合意内容の書き方

【目次】
○ 具体的な面会交流の頻度
○ 抽象的な面会交流の頻度
○ 面会交流の実施方法1
○ 面会交流の実施方法2
○ 面会交流の中傷禁止
○ 面会交流の円満実現
○ チェックシートを使ってスムーズに離婚協議書などを作成
離婚公正証書の原案や離婚協議書を自分で作成する場合、
どう書けばいいかと悩む方が多いので具体的な書き方をお伝えします。
協議離婚は夫婦間の話し合いで解決を目指すものであり、
面会交流の合意についてもお互いが納得すれば自由に決定できます。
つまり各夫婦によって合意(記載)内容が変わるので、
書き方を丸写しするだけではなくその意味も理解するようにして下さい。
面会交流については10項目以上の合意をするご依頼者様もいらっしゃいます。
第3条 具体的な面会交流の頻度
甲及び乙は、長男に対する面会交流について、
1か月の内1回、毎月第2土曜日に実施することで合意した。
面会交流の頻度は夫婦間の話し合いで決定することができます。
頻度については具体的な回数(月○回)で合意する夫婦が多いですが、
子供の年齢などに応じて抽象的な合意(子供が望めば)でも問題ありません。
面会交流の頻度を具体的にすることでルール化されますが、
想定外の事態が起きた場合は対応が難しいというデメリットがあります。
例えば、子供が病気になって面会交流ができない場合、
代替日を作るか、作らないかで揉めて考えが衝突する可能性があります。
こういう訳でメリットもあれば当然にデメリットもあります。
第3条 抽象的な面会交流の頻度
甲及び乙は、長男に対する面会交流について、
甲又は長男が希望した場合に実施することで合意した。
頻度という言葉を聞くと回数を決めなければいけないと考えがちですが、
この書き方のように回数ではなくて抽象的な合意をしても問題はありません。
離れて暮らす親と子供の関係が良好な場合は、
「○○が希望した場合」という書き方をすれば柔軟な対応ができます。
子供が中学生以上の場合、このように回数を設けないケースが多いです。
注)あくまでも子供の精神年齢に左右されるので絶対的な基準ではないです。
最後に面会交流は子供の成長のために実現するものであり、
子供が望むのであればできる限り叶うようにしてあげて下さい。
第3条 面会交流の実施方法1
甲及び乙は、長男に対する面会交流について、
午前10時から午後5時まで、○○公園にて実施することで合意した。
面会交流の実施方法は夫婦間の話し合いで決定できるので、
お互いが納得できれば細かい条件を定めてルール化することも可能です。
ただここまで細かい条件だと柔軟な面会交流ができないので、
この合意をするご依頼者様は少なく珍しいケースだとご理解下さい。
例)離婚後、天気が悪くても公園で実施するのか揉めてしまう。
離婚後もわだかまりが残っている夫婦の場合、この合意になることが多いです。
ちなみにこの書き方以上に細かい条件を決めるご依頼者様もいらっしゃいます。
例)待合せ場所は○○駅の1番出口の改札にする。
第3条 面会交流の実施方法2
長男に対する面会交流については、
乙が長男に同伴して参加するものとする。
最近、この同伴に関する合意をされるご依頼者様が多いです。
子供が幼い間は付き添いたいという理由以外にも、
離婚原因などをきっかけに夫への不信感から合意するケースもあります。
例)夫が面会交流の場に新しいパートナーを連れてきそうな気がする。
第3条 面会交流の中傷禁止
甲は面会交流の場において、長男に対して、
乙に対する中傷を含む言動をしてはならない。
ここ数年、この中傷禁止の合意をするご依頼者様が多いです。
離婚原因によっては元妻への不満が解消されていないこともあり、
子供との面会交流の場で不満や悪口(中傷)を言わないという合意となります。
例)お母さんのせいで一緒に暮らせなくなったと子供に伝える。
面会交流は「子供の成長のため」という実施目的を忘れてはいけません。
第3条 面会交流の円満実現
甲及び乙は、円満な面会交流を実現するために、
長男に他方への中傷を含む言動をしてはならない。
この円満実現に関する合意をされるご依頼者様は非常に多いです。
子供に対して親権者(主に母親)は日常生活で中傷をしない、
離れて暮らす親(主に父親)は面会交流をする時に中傷をしないという約束です。
離婚することで夫婦は他人になりますが親子関係は続くので、
面会交流は「子供の成長のため」という目的を忘れないための大切な合意です。
チェックシートを使ってスムーズに離婚協議書などを作成
離婚協議書や離婚公正証書作成のご依頼を頂いた場合、
シンプルでわかりやすい離婚チェックシートの送付から始めます。
〈離婚チェックシートとは?〉
① 全13ページ63個の離婚条件を掲載
② わかりやすいように○×回答形式を多く採用
③ 協議離婚の情報や条件を集める時間を省略できる
離婚チェックシートには①~③の特徴があります。
つまり離婚協議書や離婚公正証書の完成期間、離婚届の提出時期を早めることができます。
また離婚チェックシートを利用すれば離婚協議を効率よく進めやすくなるため再協議の回数を減らせます。
なお、面会交流に関する選択肢は多数掲載しています。今回紹介した面会交流の文例は一部となります。
離婚チェックシートを利用されたご依頼者様の声の一部(抜粋)をお伝えします。
〈ご依頼者様の声の一部抜粋〉
・こちらの希望を書いていくと、
整理されて、先々のことが見通せてすっきりしました。
・作成に必要なチェックリストもシンプルでわかりやすく、
自分で作成していたらもっと時間がかかったと思います。
離婚チェックシートの詳細はこちらのページに掲載しています。
また当事務所では初回無料相談を実施しておりますのでお気軽にご利用下さい。